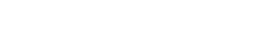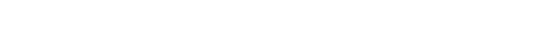こんにちは。アンテナライターチームです。
この記事で分かること
- ・建設業にマーケティングが必要な理由
- ・自社の強みや専門性を明確にする方法
- ・具体的なマーケティング施策の流れと手順
- ・建設業に有効なマーケティング媒体と、その選び方・活用ポイント
目次
建設業は「重層下請構造」のような古い習慣が未だ残っており、元請けに頼った経営を行っている企業も多いのが現状です。
しかし、下請けの仕事だけでは経営を安定させるのは難しいのではないでしょうか。
既存の構造から脱却し、自社の売上を安定させるために役立つのがマーケティングです。
本記事は建設業のマーケティングについて、必要な理由や取り組む際の手順、具体的な媒体などを解説します。
マーケティングとは?

マーケティングとは、商品やサービスが売れる仕組みを作ることです。
お客様のニーズの合った商品やサービスをつくり、必要としているターゲット顧客へ向けて発信して
効果を検証する一連のプロセスを指します。
似た用語で「セールス」がありますが、こちらは売ることを目的としていることが多く、売れる仕組みをつくるマーケティングとは趣旨が異なります。
建設業にマーケティングが必要な理由

建設業の仕事の受注は下請けや紹介が多く、マーケティングは関係がないと思われるかもしれません。
しかしマーケティングを学び、実行すれば下請けからの脱却や、自社ブランドの確立など、さまざまなメリットを享受できます。
1.下請から抜け出す
昨今、建築業でマーケティングが重視されるようになった背景には、「重層下請構造」による経営の行き詰まりによるところが大きいでしょう。
重層下請構造とは、建設業や鉄鋼業、造船業では一般的な下請け形態で、請け負った仕事を下請けに依頼し、依頼を受けた会社はさらに下請けに依頼するといった構造を指します。
作業間の連絡や調整がしづらく、責任の所在が不明瞭になることから問題視されている構造ではあるものの、未だ大幅な改善はされていません。
重層下請構造では下請けの末端へいくほど報酬が下がるため、元請けに頼っていては経営が苦しくなる一方です。
マーケティングに取り組めば、この構造から抜け出し、顧客から直接受注することが可能になります。
2.専門性を出す
マーケティングの過程で自社の分析を行い、専門性を明確にすれば、ターゲット顧客へ自社の強みをアピールできます。
自社の分析では、経営理念や現状の経営状態、人材や資金などリソースの確認などを把握、分析します。
その結果を競合他社と比較することで、自社の強みが分かるわけです。
また強みを専門性と捉え、ブランディングを行うと、他社との差別化が図れるでしょう。
3.認知度を高め集客力をつける
マーケティングで成果を上げると、これまでより認知度が高まります。
認知度が高まれば、それだけ集客が有利になり、仕事を獲得しやすくなります。
認知度を高めたあと、適切な戦略を基にSNSや広告などに取り組めば、新規顧客やリピーターの獲得に高い効果を発揮できるでしょう。
マーケティングのフロー

この章ではこれからマーケティングに取り組む方に向けて、全体的なフロー(流れ)を解説します。
1.市場調査を行う
自社の商品やサービスが顧客に求められていなければ、売れにくいのは当たり前です。
市場調査を行い、ターゲット顧客が何を求めているのかを把握します。
2.戦略を練る
市場調査を基に、どのような商品やサービスをリリースするのかを考えます。
また、価格やリリースのタイミング、注文や配送システムなどの戦略を練ります。
3.広告・宣伝を行う
短期間で多くの顧客にアピールするためには広告を出し、宣伝を行います。
近頃は高額で手間のかかるテレビCMや新聞、雑誌などのオフライン広告より、低予算からはじめられるリスティング広告やSNS広告など、WEBを活用したオンライン広告が主流になりつつあります。
4.効果・検証を行う
これまで取り組んでいたことがどのくらい売上につながったのか、費用対効果などを含めて検証をします。
また売上につながっていなくても、認知度は向上したか、見込み客は増えたのかなども検証を行い、改善策を考えていきます。
建設業のマーケティングを成功に導くには

マーケティングのフローを確認したあとは、具体的になにをしていくのか見ていきましょう。
マーケティングにおいて、最も重要な要素の一つがターゲット顧客の選定です。
ターゲット顧客に向けて、自社の強みをどのように伝えるかで結果は大きく変わってきます。
またその際、伝える方法や利用する媒体の選択も大切です。
これらのポイントを把握した上で、自社のターゲット顧客を見定めるために役立つ、マーケティングの主要なフレームワークを2つ紹介します。
3C分析とSWOT分析
マーケティングの代表的な手法として「3C分析」と「SWOT分析」と呼ばれるフレームワークがあります。
これらの手法を使うことで、自社の業界内における立ち位置や、顧客のニーズなど俯瞰して捉えることができるため、最適なマーケティングが行いやすくなります。
3C分析とは
3C分析とは、Customer(市場・顧客)、 Competitor(競合)、Company(自社)の略称で、マーケティングの方向性を定めるために使用されるフレームワークです。
下記の3点を分析し、どのようにマーケティングを展開していくのか定めていきます。
1. Customer:顧客・市場の調査
2. Competitor:競合他社の調査
3. Company:自社の調査
1.Customer:顧客・市場の調査
自社が提供する商品やサービスについて、顧客のニーズや市場における価値を調査します。
まずは自社の強みを明確にするためにも、自社の理念や得意分野、これまでの施工実績などを整理し、把握しましょう。
その強みを生かせる業務が市場にどのくらいボリュームがあるのかを調べ、今後の成長予測を立てます。
また、自社の強みを生かせる業務について、顧客側の立場になって考えることも大切です。
依頼する際はどのような方法で建築会社を調べ、連絡するのかを把握することは、これから展開するマーケティングにおいて重要な意味を持ちます。
2.Competitor:競合他社の調査
自社が市場で生き残るためには、競合他社の調査は必須と言えます。
競合他社と差別化を図り、自社の優位性をアピールしていくことがマーケティングの基本姿勢です。
まずはWEBに公開されている情報を基に、市場シェアを調べてみましょう。
新規参入や事業撤退などの傾向を掴み、市場全体の変化を予測します。
また、競合他社のマーケティングやセールス方法を調査すれば、自社のマーケティングの参考になります。
その際に注目するのは、アピールポイントや言葉遣いや画像などに表現方法、顧客の獲得方法、収益構造などです。
競合他社の手法を参考にしつつ、自社の強みを生かす方法を考えましょう。
3.Company:自社の調査
最後に現状を把握するために、自社の調査を行います。
把握すべき主な項目は下記の5点です。
・自社の企業理念やビジョン
・既存事業の現状(市場内のシェア率や売上、商品やサービスのラインナップなど)
・自社(既存事業)の強みや弱み
・「ヒト」「モノ」「カネ」のリソース
・資本力や資金力
これらの項目を把握し、分析することで市場におけるポジションを明確にしましょう。
SWOT分析とは
SWOT(スウォット)とは、Strength(強み)・Weakness(弱み)・ Opportunity(機会)・Threat(脅威)から名付けられた造語です。
自社の事業状況をこの4つの項目で整理することで、事業の戦略方針が明確になります。
SWOT分析では、自社の事業状況を内部環境と外部環境に分け、さらにそれぞれプラス要因とマイナス要因に分けて考えます。
| プラス要因 | マイナス要因 | |
|---|---|---|
| 内部環境 | Strength(強み) | Weakness(弱み) |
| 外部環境 | Opportunity(機会) | Threat(脅威) |
各要素が整理できたら、要素同士を掛け合わせて戦略を練っていきます。
この方法はクロスSWOT分析と呼ばれ、戦略をより明確にする効果があります。
クロスSWOT分析のマトリクスは以下の通りです。
| Strength(強み) | Weakness(弱み) | |
|---|---|---|
| Opportunity(機会) | 強みを最大化させる | 弱みを克服し機会を生かす |
| Threat(脅威) | 強みを生かし脅威を避ける | 弱みを把握し脅威を抑える |
イメージが湧きやすいように具体例を挙げていきましょう。
・Strength(強み)×Opportunity(機会)の例
Strength(強み)が「手厚いアフターサービス」、Opportunity(機会)が「顧客ニーズの多様化」だとすると「既存顧客からの要望やクレーム内容を新サービスの設計に生かす」などが考えられます。
・Strength(強み)×Threat(脅威)の例
Strength(強み)が「手厚いアフターサービス」、Threat(脅威)が「大手企業の新規参入」の場合は「大手企業では実現が難しい充実したアフターサービス」をアピールするといった方法があります。
このように要素同士を掛け合わせ、自社の強みや弱みをうまくコンロトールし、最適なマーケティング戦略を立てるようにしましょう。
顧客層を絞り込む

前章で解説した3C分析やSWOT分析を活用し自社の強みが把握できたら、売る相手、つまり顧客層の絞り込みを行います。
一般的に顧客層を決める際は「どのような人物」なのかを詳細に考えることが重要です。
例えば、年齢・性別・役職・勤務年数・年収・家族構成・居住地などを設定し、顧客の属性や環境を明確にします。
これは「ペルソナ設定」と呼ばれるもので、マーケティングにおいてターゲット顧客の設定で多用される手法です。
次に設定した顧客が「どのような理由があると自社に依頼したいと思うのか」を客観的に考えます。
あくまで自社の強みを押し付けるのではなく、困っている顧客はなにを求めているのかを考えることが大切です。
3C分析やSWOT分析で明確になった市場の状況やニーズなどを考慮しながら、適切に顧客層を絞り込みましょう。
マーケティングの目的と目標を定める

マーケティングを行うためには、目的と目標を定める必要があります。
目的と目標は似た言葉ですが、下記のように意味が異なるため、混同しないようにしましょう。
| マーケティングの目的 | マーケティングを通じて成し遂げたいこと |
| マーケティングの目標 | 目的を達成するための到達水準(必要な成果) |
このように「目的が最終的なゴール」に対し、目標は目的を達成するための通過点です。
したがって目的は1つですが、目標は段階ごと設定するため複数であることが一般的と言えます。
では、目標設定の具体例を見ていきましょう。
マーケティングの目的(例)
・元請けに頼った経営からの脱却
マーケティングの目標(例)
・ターゲット顧客における認知率を60%以上にする
・毎月5件の新規顧客獲得
・リピーター率を10%向上させる
・イベントでの成約率を5%向上させる
・自社WEBサイトが展開しているコンテンツの検索順位を上げる
上記「マーケティングの目的」の項目は、ほんの一例に過ぎないため、参考程度と捉えてください。
自社の目的を達成するために必要な要素をリスト化し、具体的に数値化することで目標を明確化できるでしょう。
マーケティング媒体を選ぶ

マーケティング媒体はそれぞれ特徴があり、1つですべてを賄える媒体はありません。
自社の目的や目標に合った複数の媒体を併用することで、効果の最大化を実現できます。
そこでここでは、オフラインを含む10種のマーケティング媒体について解説します。
1. 自社サイトの運営管理
2. SEO対策
3. WEB広告
4. ランディングページ
5. ポータルサイト
6. SNS(ソーシャルメディア)の運用
7. マスメディア広告
8. チラシ・ポスティング・折込み広告
9. イベントやセミナーを主催する
10. フリーペーパー/住宅情報誌
1.自社サイトの運営管理
インターネットで調べ物をするのが当たり前となった現在では、自社サイトの充実は必須事項と言えます。
なぜなら、自社サイトは「WEBでの看板」に例えられるほど、重要な役割を担っているからです。
SNSや広告など、他の媒体で自社を知った顧客も、大半は自社サイトを確認してから購入や申し込みを検討します。
したがって、自社サイトは顧客が安心できるように、上質で堅実なイメージを打ち出すことが重要です。
また、見積事例や施工事例などを公開することで顧客の不安を軽減できるため、事例をいくつかのパターンに分けて用意しましょう。
さらに見積をシミュレーションできるシステムがあると、顧客の反応が良くなりやすいです。
2.SEO対策
SEO対策とは、Googleをはじめとする検索エンジンでキーワード検索を行った際、上位表示させるための施策を指します。
検索上位に表示されると、WEBサイトへのアクセス数が増大するため、成約数の向上が見込めます。
SEO対策は奥が深く、専門業者が多くいるほど難易度は高いですが、本質は「ユーザーの悩みを解決できているか」という点です。
具体的な方法は、まずターゲット顧客がどのような悩みを抱えているのかを把握し、その顧客が検索する際に使いそうなキーワードを選定します。
そして選定したキーワードをタイトルや本文に盛り込み、ターゲット顧客の悩みを解決するコンテンツ(記事)を作成するといった流れです。
そのほか、SEO対策にはさまざまなテクニックが存在しますが、まずは上記の「SEOの本質」だけ理解し、実践していきましょう。
SEO対策が功を奏すと、自社サイトへのアクセス数増加に加えて信頼性も高まります。
検索上位を維持できれば営業活動をすることなく、売上を伸ばし続けることが可能になるでしょう。
3.WEB広告
WEB広告とはインターネット上に表示される広告で、いわゆる「オンライン広告」を指します。
WEB広告のなかでも代表的な「リスティング広告」は、インターネットを利用していれば必ずと言っていいほど目にしているはずです。
リスティング広告は、検索エンジンの検索結果に連動して表示される広告で、下記のようなメリットがあります。
・検索上位記事の上部に表示できる
・ユーザーがクリックした際に費用が発生するため低予算でも広告が出せる
・検索したキーワードに連動して表示できるため見込み客にアプローチできる
・リアルタイムで広告の成果を確認できる
・短い時間で出稿、広告の停止、内容変更ができる
デメリットとしては、SEO対策と違い継続的に費用がかかることや、広告を避ける顧客が一定数
いることです。
ただしSEO対策の効果が出てくるまでには長い期間を要するため、リスティング広告などのWEB
広告と併用することをおすすめします。
特に新しいプランやキャンペーンなどを行う際には、即効性の高いWEB広告を活用すると良いで
しょう。
4.ランディングページ
ランディングページとは、広告バナー等をクリックした先にある「販売に特化したWEBページ」のことです。
多くの場合、1つのページで構成されており、セールスライティングなど顧客の購買意欲を後押しする仕掛けが施されています。
明確に売りたい商品やサービスがある場合に有効な手法で、記載された内容によっては高い確率で成約に繋がります。
だだし、ランディングページは商品やサービスに興味がある顧客を対象にしているため、興味のない段階で訪れても効果が薄いといった点がデメリットです。
ランディングページを訪れる前に、広告やWEBコンテンツ等でいかに興味を持ってももらうかが、成功のポイントとなるでしょう。
5.ポータルサイト
ポータルサイトは、検索するユーザーが求める情報に辿り着くまでの繋ぎ役を担うホームページのことです。
身近なところでは、GoogleやYahoo!がポータルサイトに該当します。
建設業専門では、中大規模木造建築ポータルサイトなどが有名です。
ポータルサイトを活用することで、自社サイトでは接点のなかった顧客へのアプローチが可能になります。
また、建設業関係のポータルサイトを訪れるユーザーは明確な目的のあることが多いため、成約に繋がりやすい傾向が見られます。
6.SNS(ソーシャルメディア)の運用
ターゲット顧客が若い層の場合はSNS運用が効果的です。
自社のアカウントで魅力的な発信を続けるとフォロワーが増え、信頼度が増し、やがて売上に繋がります。
発信の内容はターゲット顧客に合わせて行います。
例えば、自然素材を重視している顧客がターゲットなら、天然木についてのうんちくや、木材ごとに美しい木目の画像を投稿すると喜ばれるはずです。
自社の企業理念に関する信念について発信し続けると、熱烈なファンがつく可能性もあります。
また、ターゲット顧客が好みそうな作業風景の動画も高い効果が期待できます。
しかしSNSでは投稿が表示されても、すぐに新しい投稿が表示され、情報が上書きされるため、定期的な更新が必要です。
1日1投稿以上を目指し、アクティブに運用していきましょう。
7.マスメディア広告
マスメディア広告とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌の4媒体に掲載される広告のことで、「マス広告」や「4マス広告」と呼ばれることもあります。
不特定多数の視聴者や読者に向けてアピールできるため、ターゲット顧客以外のユーザーにもアプローチが可能です。
大勢の幅広い世代に向けて発信できるため、認知度を高める効果に秀でています。
H3: 8.チラシ・ポスティング・折込み広告
チラシやポスティング、新聞の折込み広告は昔からあるオーソドクスな手法ですが、現在でも高い効果が期待できます。
新聞の折り込み広告は、PCやスマートフォンを日常的に使用していない高年齢層やファミリー層に有効で、チラシやポスティングは新聞を購読していない世帯にも届けられるメリットがあります。
認知度を高めたい場合は新聞広告、地域を絞ってアプローチしたい場合はチラシやポスティングが最適です。
9.イベントやセミナーを主催する
「住まいのなんでも相談会」「リフォームの悩み相談」などのイベントを定期的に行うと、新規顧客獲得に加え、見込み顧客の悩みを直に聞くことができます。
3C分析やSWAT分析でターゲット顧客層やニーズを把握することも大切ですが、現実とは異なるケースもあります。
イベントやセミナーなどを通して見込み顧客の「本当の悩み」を知り、マーケティング戦略の精度を上げていきましょう。
10.フリーペーパー/住宅情報誌
フリーペーパーや住宅情報誌に自社の情報を掲載し、宣伝を行います。
こちらは先ほど紹介したチラシと特徴は似ていますが、さらに情報量を多くするイメージです。
また、チラシは幅広い層へのアプローチなのに対し、フリーペーパーや住宅情報誌は顕在層への訴求に有効です。
まずは身近で継続的なマーケティングが出来るWEB・SNSで

10種類の主なマーケティング媒体について解説してきましたが、最初からすべてに取り組むと作業が多すぎて混乱するかもしれません。
したがって、まずは低コストから始められるWEBサイト(自社サイト)やSNSに取り組んでみてはいかがでしょうか。
WEBサイトやSNSは他の媒体と比べると身近に取り組めるほか、継続的に効果を発揮できます。
特にWEBサイトは1度作ると資産として永続的に残るため、必ず作っておきましょう。
また、ほかの媒体や施策を始めるとしても、この2つと連動することが多いことから、最初に取り組む媒体として最適です。
マーケティング施策はCWMをご利用ください!

これまで建設業のマーケティングについて解説してきましが、社内にマーケティングを担当する適任者がいない、ほかの業務が忙しく専任者を配置できないといった問題もあるのではないでしょうか。
弊社のCWM(クラウドWEBマスター)は月額29,800円で、ホームページやSNSなどデジタルに関することを何でも相談できるサービスです。
大手サイトを数多く手掛ける弊社エンジニアが貴社の情報システム部として稼働します。
PCや社内ネットワークの困ったことからホームページの制作作業や高度なICTの運用まで、なんでもご用命ください。
デジタルやホームページの専門担当者が企業の課題をヒアリングしご提案。WEB・ICTの課題を解決します。
CWMの資料請求
https://cwm.jp/document/
CWMに関するお問合せ
https://cwm.jp/contact/
まとめ

建設業者が自社の強みを評価してくれる顧客と出会うためにはマーケティングは必須です。
マーケティングに取り組みエンドユーザーから直接受注できれば、重層下請構造から抜け出せるため、安定した売上を上げることが可能になります。
自社の強みを押し出す戦略で臨めば、競合他社との価格競争に巻き込まれる心配もありません。
まずは3C分析とSWOT分析に取り組み、市場における自社の状況やターゲット顧客のニーズを探っていきましょう。
とはいえ、具体的になにから取り組んだらよいか分からないといった場合は、お気軽にお問い合わせください。
CWMが貴社のマーケティングを全力でサポートいたします。